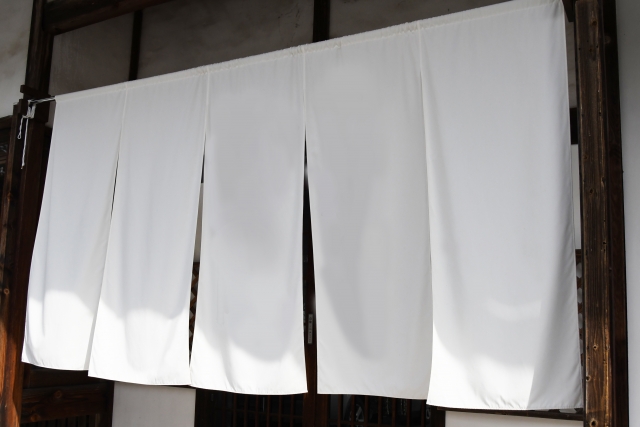宮城県内でも近年、薬局の第三者承継や買収といった「薬局M&A」が増えつつあります。そんな中で、譲渡価格の中に含まれることが多い「営業権(のれん代)」について、正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
本コラムでは、薬局M&Aにおける営業権とは何か、どのように評価されるのか、譲渡側・譲受側の双方が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
営業権(のれん代)とは?
営業権(のれん代)とは、「企業が長年にわたって培ってきたブランド力や顧客基盤、立地、信頼、ノウハウ」といった無形資産に対して支払われる価値を指します。これは貸借対照表には載っていない“見えない資産”であり、薬局の買収においても大きな価値を持つ要素の一つです。
たとえば、同じような立地・規模の薬局でも、患者からの信頼が厚く、安定した処方箋枚数を継続的に得ている薬局であれば、その「営業の仕組み」自体が高い価値を生みます。これが、営業権として評価されるのです。
営業権はどのように評価されるのか?
薬局M&Aにおいて、営業権は次のような観点から評価されます。
1. EBITDAに基づく評価
EBITDA(営業利益+減価償却費)は、企業が本業でどれだけのキャッシュを生み出しているかを示す指標で、薬局M&Aでは基本的な評価軸となります。
このとき、薬局の経営に直接関係ない費用(オーナーの私的な経費や役員報酬の過大部分など)は調整され、より実態に即した利益から営業権が算出されます。
2. 地域性と競合状況
宮城県のように都市部と郊外で医療資源の分布に差がある地域では、営業権の評価にも地域性が大きく影響します。特に処方箋の多くを門前医療機関から得ている薬局では、その医療機関との関係性や医師の年齢、後継者の有無が営業権の価値を左右します。
たとえば、門前の医師が高齢であり、後継者が決まっていないケースでは、将来的な処方箋の減少リスクが高まり、営業権の評価は低くなります。逆に、後継者が明確で地域に根差した医療提供が継続する見込みであれば、営業基盤は安定し、営業権の価値も維持されやすくなります。
3. 処方箋枚数・売上の安定性
処方箋枚数の年間推移や季節変動の安定性、処方元の多様性も重要な評価ポイントです。門前一極依存型の薬局より、複数の医療機関から処方を受けている薬局の方が、リスク分散が効いており、営業権が高く評価される傾向にあります。
譲渡側が注意すべきポイント
1. 営業権の根拠を明確にしておく
営業権は目に見えない資産だからこそ、「なぜこの金額なのか」を丁寧に説明できる準備が重要です。過去の処方箋枚数、地域での評判、門前医療機関との関係などを資料化しておくことで、交渉がスムーズに進みます。
特に、門前医師の年齢や後継の有無、今後の診療体制の見通しについても記載があると、買い手の安心感につながり、営業権を高く見積もってもらいやすくなります。
2. EBITDAを最大化する経費整理
営業権はEBITDAに大きく左右されます。したがって、譲渡前に「薬局経営に不要な費用」を見直し、調整EBITDAを高めておくことが、営業権の価値向上につながります。
3. 売却時期の見極め
営業権が最も高く評価されるのは、経営が順調で、かつ門前医師の診療継続が見込める時期です。逆に、門前の医師がすでに高齢でリタイア間近な状況だと、評価額が下がってしまうため、将来的な医療機関の動向を見極めて売却時期を検討することが重要です。
譲受側が注意すべきポイント
1. 営業権の金額と根拠を精査する
営業権が高額に設定されている場合には、処方箋枚数の安定性、地域の医療需要、門前医師の診療継続の見通しなど、あらゆる観点から裏付けを確認しましょう。
とくに医師の年齢や後継者の存在は、薬局経営の継続性に直結する要素です。買収後に門前が閉院となれば、処方箋が激減し、M&A自体が不調に終わるリスクもあります。
2. 営業権の投資回収可能性を分析
EBITDA倍率や営業権の回収年数をシミュレーションし、現実的な回収計画が立てられるかどうかも重要です。営業権の支払が経営を圧迫するようでは、買収後の安定運営が困難になります。
宮城県における薬局M&Aと営業権の傾向
宮城県内では、仙台市を中心にM&Aの事例が増加傾向にあります。一方で、郊外の地域では高齢化と後継者難が進んでおり、門前の医療機関が今後どうなるかは大きな検討材料となっています。
とくに、門前医師の高齢化と後継未定といった薬局は、営業権の評価が下がる傾向があり、譲渡側にとっては早期の意思決定が求められる状況です。
まとめ:営業権の背景にある「将来性」を見極める
薬局M&Aにおける営業権(のれん代)は、「今ある利益」だけでなく「将来にわたる利益の再現性」に基づいて評価されます。門前医師の年齢や後継者の有無は、まさにその将来性を左右する重要なファクターです。
譲渡側は、自身の薬局が持つ営業的価値を整理・可視化し、より良い評価を受けられるよう準備を行いましょう。譲受側は、数字の裏にある“リスクとチャンス”を見極める目を養い、納得できるM&Aを目指すことが大切です。