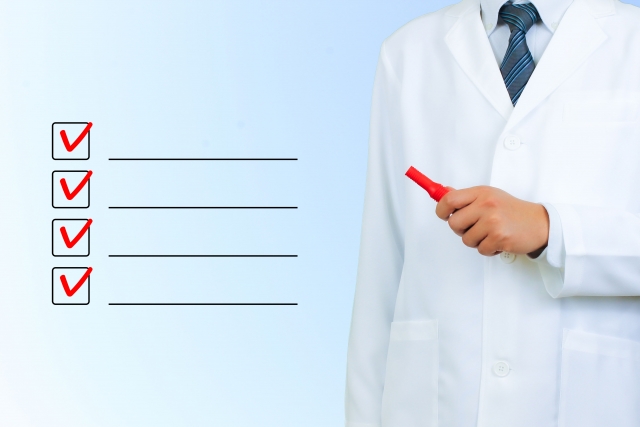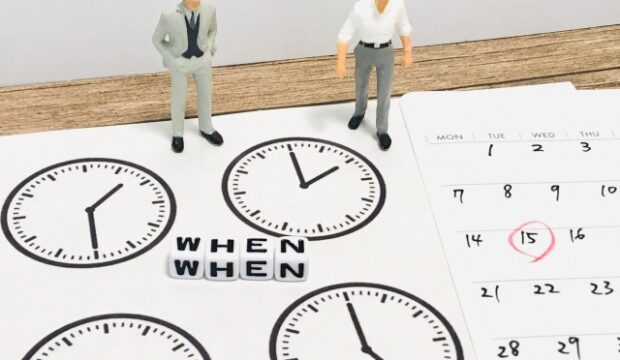はじめに
2025年9月10日、厚生労働省は中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開催し、2026年度の調剤報酬改定に向けた議論を本格的にスタートさせました。今回の改定において焦点となっているのが「調剤技術料」と「薬学管理料」の評価です。薬局経営の根幹を支えるこの2つの要素について、診療側と支払い側の意見は大きく分かれています。
本コラムでは、2026年度調剤報酬改定に向けた議論のポイントを整理し、薬局経営者にとってどのような影響が予想されるのかを考察していきます。特に「地域医療を担う薬局の経営維持」「薬剤師の対人業務評価」「後発医薬品の位置づけ」「かかりつけ薬剤師の普及」「薬剤師の偏在」といった重要論点を中心に、今後の方向性を探ります。
1. 調剤報酬改定をめぐる全体像
調剤報酬は、薬局の経営基盤であると同時に、薬剤師の役割や地域医療における薬局の機能を評価する制度です。2026年度の改定に向け、厚労省は以下の2点を大きな論点として提示しました。
- 地域の医薬品供給拠点としての薬局機能をどう評価するか(調剤技術料:調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算など)
- 薬剤師の対人業務をどう拡充・評価するか(薬学管理料:調剤管理料、かかりつけ薬剤師指導料など)
つまり「薬局は薬を渡す場所から、医療を支える拠点へ」「薬剤師は薬を調剤するだけでなく、患者に寄り添い支援する存在へ」という方向性を、どのように点数に反映させるかが議論の中心となっています。
2. 調剤技術料の評価をめぐる議論
2-1 診療側の主張:調剤基本料で下支えを
日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、「地域医療を支える薬局の経営は特に厳しく、調剤基本料を中心とした評価で下支えが必要」と強調しました。確実な賃上げを実現するためには、ベースとなる調剤基本料に厚みを持たせることが不可欠であるという立場です。
特に中小薬局は人件費や備蓄コストが経営を圧迫しており、基本料で安定収入を確保できなければ、地域医療から薬局が消えてしまうリスクがあります。「保険あってサービスなし」という状況を回避するためにも、基本料の強化が求められているのです。
2-2 支払い側の主張:一本化と加算・減算での差別化
一方で、支払い側の松本真人氏(健康保険組合連合会理事)は「調剤基本料は最低限の水準に一本化し、機能に応じて加算や減算で差をつけるべき」と主張しました。
背景には、薬局機能の多様化や敷地内薬局の増加があります。特別調剤基本料を含め、複雑化した基本料体系をシンプルに整理し、真に地域医療に貢献する薬局に重点的に評価を配分したい、という考えです。
3. 地域支援体制加算をめぐる課題
2024年度改定で大幅に見直された地域支援体制加算は、医薬品備蓄の充実を要件としています。厚労省のデータによれば、多くの薬局が基準ギリギリの1200品目前後で備蓄を行っており、「加算を取るための備蓄」にとどまっている現状が明らかになりました。
診療側は「地域医療を支える薬局が正しく評価される仕組みが必要」と訴えていますが、支払い側は「加算のための備蓄に意味はなく、地域医療に本当に貢献しているかが重要」と指摘しています。
今後は、単なる数量基準ではなく、地域の実情に応じた柔軟な評価軸が検討される可能性があります。
4. 後発医薬品調剤体制加算の行方
後発医薬品の数量シェアは2024年9月時点で85.0%に達し、一定の成果を上げています。しかし支払い側は「すでに後発品使用は当たり前であり、引き続き加算を維持する意義は薄い」と主張しています。
代わりに「調剤割合が低い場合の減算」や「医薬品全体を分母とした指標による評価」への転換が検討されています。診療側は「供給不安に対応する薬局現場を支えるために評価は不可欠」と反論していますが、2026年度改定では加算縮小や減算中心へのシフトが現実味を帯びています。
5. 薬学管理料とかかりつけ薬剤師制度の課題
5-1 調剤管理料の見直し
調剤管理料について、支払い側は「処方日数に応じた点数評価は問題が多い」と指摘しています。2024年度改定で一部見直しが行われましたが、「一律点数にすべき」という意見も強く、さらなる修正が予想されます。
5-2 かかりつけ薬剤師の普及
かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料は増加傾向にありますが、患者調査では「かかりつけ薬剤師を持ちたい」と答えたのは全体の40.1%にとどまりました。届出薬局数は全体の6割に達しても、算定回数は130万回程度とまだ限定的です。
診療側・支払い側ともに「普及は不十分」と認めており、今後は評価のあり方を再検討する必要があります。特に「患者に選ばれる薬剤師」を育てることが普及のカギとなるでしょう。
6. 薬剤師の偏在問題
総会では薬剤師の地域偏在についても議論されました。薬局数は都市部で増加し続けている一方、病院薬剤師数は全国的に不足しています。
病棟業務に必要な薬剤師の不足は深刻であり、日本医師会や慢性期医療協会からも「病院薬剤師の養成強化が喫緊の課題」との声が上がりました。支払い側からは「薬局から病院へ人材をシフトさせるため、調剤報酬を通じて誘導できないか」という意見も出ています。
これは薬局にとって「人材確保競争が一層激化する」ことを意味します。今後の報酬改定では、人材配置や勤務実態に応じた評価も検討される可能性があります。
7. 2026年度改定の方向性と薬局経営への影響
以上を踏まえると、2026年度調剤報酬改定は次の方向性が見込まれます。
- 調剤基本料は一本化・シンプル化される可能性が高い
- 地域医療貢献や対人業務への評価を重視した加算体系へシフト
- 後発医薬品加算は縮小・減算方式への転換が検討される
- かかりつけ薬剤師制度の普及促進に向けた新しい評価の導入
- 薬剤師の偏在是正に資する仕組みの導入
薬局経営者にとっては「単に薬を調剤するだけでは評価されない」時代が一層鮮明になります。地域医療への貢献、患者支援の実績、薬剤師の専門性発揮が、報酬にも直結することになるでしょう。
おわりに
2026年度の調剤報酬改定は、薬局経営のあり方を大きく左右する分岐点となります。特に中小薬局にとっては「生き残れるかどうか」の試練の時代とも言えるでしょう。
今後の議論の行方を注視しつつ、各薬局が「どのように地域に貢献し、患者に選ばれる存在になるか」を具体的に考え、行動に移していくことが求められます。
地域に根ざす薬局が持続的に運営されるためには、報酬改定を受け身で待つのではなく、むしろその変化を経営戦略に組み込み、積極的に対応する姿勢が必要です。
[参考資料] ・厚生労働省:中央社会保険医療協議会総会(第616回)議事次第

<注意点>
本記事は事実情報を中心に掲載していますが、一部筆者の見解が盛り込まれています。また、閲覧者様の記事閲覧時に最新でない情報が掲載されていることも考えられます。記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねますので、各々にて最新情報および掲載元の情報をご確認ください。